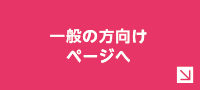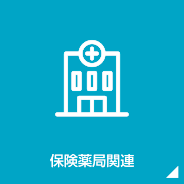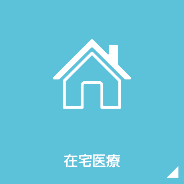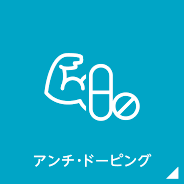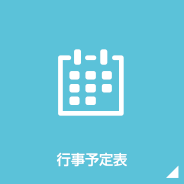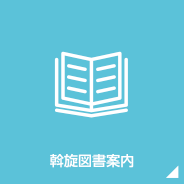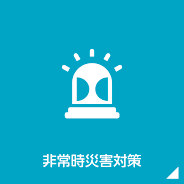学校薬剤師 環境衛生検査実施要項【検査目的と事後措置】
| 検査項目 | 検査目的・備考 | 検査結果を受けての事後措置 | その他 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため |
・窓側の温度が高いときの対応として、カーテンの使用やひさしの設置、ツル植物による壁面緑化がある。ただし、照度の低下に注意する。 |
|
| 湿度 | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため |
・相対湿度が30%未満の時は適切な措置を講じる必要があるが、加湿器を利用する際には結露やカビの発生しやすくなることから過度な過失に注意する。 |
|
| CO₂ | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため |
・1500ppmを超えた時は換気を行うようにする。 |
|
| 気流 | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため |
・0.5m/秒超の気流が生じている場合には、気温、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにする。 |
|
| CO | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため。 |
・6ppmを超えた場合はその原因を究明し適切な措置を講ずること。発生源として考えられるのは主に室内における燃焼器具の使用である。 |
|
| NO₂ | 児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため。 |
・基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の発生を低くする等適切な措置を講じる。 |
|
| 揮発性 有機化合物 |
児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため。 |
・基準値を超えた場合は、その発生の原因を解明し、換気を励行する。同時に汚染物質の発生を低くする等適切な措置を講ずる。 |
|
| ダニ・ アレルゲン |
児童生徒の快適性のため、より良好な温熱環境と空気清浄度を保つ維持管理が望まれるため |
・基準値を超える場合は定期的なメンテナスを行った電気掃除機で日常的に掃除を丁寧に行うこと。また、長期休暇中にダニ用燻煙剤を実施することも検討する。 |
|
| 照度 | 学校での照明は視対象物を見やすくすることを補助し、視力への悪影響を防止し、学習能率の向上を図るうえで大変重要であるため。 |
・暗くなった光源や切れている光源は、蛍光灯等の劣化やその他の要因によるものか確認し、光源の清掃や交換・修理を行っても照度が不足する場合は増灯を検討する事。 |
|
| まぶしさ (グレア) |
学校での照明は視対象物を見やすくすることを補助し、視力への悪影響を防止し、学習能率の向上を図るうえで大変重要であるため。 |
・まぶしさを起こす光源を覆うか、視野に入らないような措置を講じることとする。教壇の教員から児童生徒等の方を見た時も同様に考える。 |
|
| 騒音 | 騒音による学習能率の低下を防ぎ、また心理的な不快感を来すことを防止するため。 |
・校内の騒音に対しては授業の時間割、教室の配置を配慮するなどして影響を少なくする。具体的には音を出す教室は互いになり合わせにする。音を多く出す特殊教室は午後の授業の少ない教室近くに配置するなど検討する。廊下や階段の足音については履物の種類の制限、机やいすの防音対策も有効。 |
|
| 飲料水 | 水道水が汚染されると、感染症のみならず様々な疫病をもたらす危険な媒体になるため。 |
◎原水が井戸その他の供給源で汚染を受ける恐れがある場合 |
|
| 大掃除の 実施 |
清潔ときれいな環境は児童生徒の健康の向上やメンタルヘルスの安定に寄与するため。 |
大掃除を定期的に実施していない場合は、学校保健に位置付けるなど、計画的に行うこと。 |
|
| 雨水の排水 | 清潔ときれいな環境は児童生徒の健康の向上やメンタルヘルスの安定に寄与するため。 |
・排水が不適切な場合は、速やかにその原因を究明し、適切な措置を講じるようにする。 |
|
| 排水の施設 ・設備 |
清潔ときれいな環境は児童生徒の健康の向上やメンタルヘルスの安定に寄与するため。 |
施設・設備の故障や破損等は、速やかに修繕をする等の適切な措置を講じるようにする。 |
|
| ネズミ・ 衛生害虫等 |
有害動物に接触することに起因した人畜共通の感染症や、排泄物付着による関節汚染を受けた食品の摂取に基づく食虫毒などの被害を防ぐため。 |
・ネズミ、衛生害虫等の生息が認められた場合は、児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を行う。 |
|
| 黒板面の 色彩 |
黒板は種類によらず、適正に使用し、適正な維持管理を定期的に行い、学習効率を高めることに役立たせないといけないため。 |
・判定基準を超える場合は、板面を塗り替える等の適切な措置を講じる。 |
|
| 水泳プール の水質 |
プール由来の水系感染や感染源となる得るプール遊泳者との接触感染や飛沫感染、さらにその施設を介した媒介物感染を予防するため。 |
・水質不良時は、プール水の水質検査を行い原因究明に努め速やかに改善する。 |